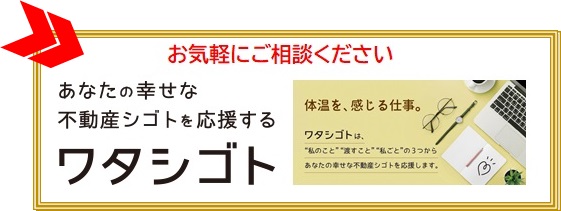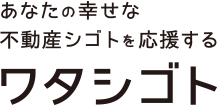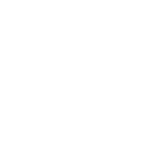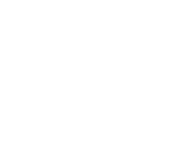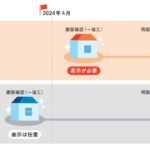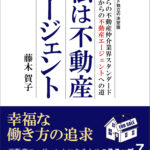境界ブロックの落とし穴!不動産取引時に気をつけるべきポイントとは?
隣家との境界線をハッキリさせ、プライバシーを守るのも大切な境界ブロック。
しかし、その境界ブロックはなにかと揉め事に発展することも多い厄介な存在でもあります。
今回は私が実際に遭遇した案件を参考にしながら、不動産取引時における境界ブロックの扱いや気をつけなければいけないポイントなどを解説していきます。
境界ブロックの法的定義
境界ブロックについては、民法第229条・境界標等の共有の推定において、次のように定義されています。
「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び塀は、相隣者の共有に属するものと推定する」
「相隣者の共有に属するものと推定する」、とされているところポイント。
つまり、「確定(みなす)」ではないということですね。
隣地境界線上にブロック塀を建てた場合、それは共有の境界ブロックだと「推定」されます。
築何十年もたっている境界ブロックの場合、それが誰の所有物かを判明することが難しく、共有所有物とみなされるため、勝手に壊したり立て直したりすることはできません。
しかしもしどちらかがその境界ブロックは自分のものだと主張し、境界ブロックが自分の敷地内にあることや、自分がそのための資金を出したことなどが証明できた場合は、その人の所有物となります。
そうした面倒事を避けるため、最近では境界ブロックは境界線上に折半で建てるということは減ってきています。
しかしもともと境界線上に建っている古い境界ブロックについて、エージェントとしてどうアドバイスするかは非常に難しい場合があるのです。
例えば、土地を購入して建物を新築する。その土地にもともと境界ブロックが建っていて、建築基準に適合するかどうか不明。というような場合に、境界ブロックをどう扱ったら良いかには注意しなければならないポイントがいくつか存在します。
今回私が扱った案件も、まさにそうした物件でした。
境界ブロックが問題となった物件の状況
今回扱った物件は、杉並区にある不動産会社が販売してる土地で、広さや立地、予算もお客様のご希望どおりのものでした。
紹介したところ、すぐに気に入られて購入する運びに。
しかし、気になったのが境界ブロックです。

このように、南側に120cmを超える高さの境界ブロックが、そして道路奥の東側(写真左奥)にも120cmを超える万年塀が建っていました。
- 南側:120cm超えの境界ブロック
- 東側:120cm超えの万年塀
この境界ブロックと万年塀それぞれで問題点と対処方法が異なっていたため、それぞれ別個に解説していきたいと思います。
南側境界ブロックの問題点と対処方法
境界ブロックについては建築条件があるため、念入りに確認しなければなりません。
2018年、地震が原因で大阪府高槻市の小学校のブロック塀が倒壊し、小学4年生の女の子が亡くなるという事故が発生しました。
その事故を契機にブロック塀についての法令遵守が厳格化され、既設ブロック塀についてもしっかりとしたチェックが入るようになりました。
設計図に既設境界ブロックの適合性や安全性を明記されていない場合は、建築に取り掛かるための確認済証が下りないこともありますから、大変です。
この南側境界ブロックも見ての通りだいぶ古いものですから、現在の法律にしっかりと適合しているかどうかを事前に確認しなければなりません。
<境界ブロックのチェックポイント>
- 既存境界ブロックについての確認がより厳格になっている。法律に適合しない場合、建築確認が下りないため、事前にしっかり確認する必要がある
もしこの南側の境界ブロックが建築基準に適合しないとなると、建て直しということになってしまいます。
このブロック塀は境界線上に建っているため、建て直しにはお隣さんの同意が必要。
共同所有物であるため、理屈ではブロック塀の建て直し時の費用は折半になるのですが、実際には言い出した方が費用を出すことがほとんどです。
もし仮に建て直しが必要という場合は、新たなブロック塀は顧客側の敷地に建てる方が後々のことを考えても穏便ですが、ただでさえ間口が狭い土地なので、ブロック塀の10cmでも厳しい。費用もかなりかかってしまうので、土地の購入そのものを見直さなければならないことにもなりかねません。
では、この南側の境界ブロックは建築基準に適合してるのか?
問題となるのが、高さです。
この境界ブロックの高さは120cm超。
建築基準法によると、120cmを超えるブロック塀には風や地震で倒れないようにするための控え壁(控柱)を塀の長さ3.4mごとにつけなければなりません。
調べてみると、7年前にお隣さんが家を建て替えており、その際に控え壁を施工して許可を得ていたということが判明しました。
これで、境界ブロックの建て直しは必要ありません。
ところがその後、もう一つ新たな問題が判明します。
それが、ブロック塀の上についている目隠し。

これですね。
施工を請け負う建築会社との打ち合わせの際に、この目隠しを建築の検査時までに外してほしいとお隣さんに伝えてほしいと言われたが、どうしたら良いか?という連絡がクライアントから入りました。
こちらもブロック塀についての意識はあったものの、その上についている目隠しまでは認識していなかったのです、ちょっとビックリしてしまいました。
建築会社としては、ブロック塀についての事前確認が厳しくなっているため、余計なものは外しておきたいということなのでしょう。実際に、ほかの物件で指摘を受けたこともあったそうです。
でもこれはフェンスというよりも明らかな目隠し。しかも隣地側にがっつり入っています。
こちらで目隠しについて確認してみると、書面こそ交わしてないものの、土地の前所有者とお隣さんで話し合って取り付けものとのこと。
お隣の敷地内にあるため、こちらで勝手に取り外すわけにもいきませんし、無理にお願いしてお隣さんとの関係が悪くなることも絶対に避けたい。
そこで、杉並区の建築指導課に電話をして聞いてみました。
するとブロック塀については建築基準法の決まりがあるが、目隠しについては指導するものがない。そのため、安全性については建築をする設計士が判断するべきもの。また隣地(他人)の所有物について撤去を命じることはできないとのことでした。
であれば、話は簡単です。
建築会社(設計士)が目視なりなんなりで安全性を確認し、それを担保すれば良い。
しかし私が建築会社にそう伝えても、建築会社は納得しないのです。基準がないため、自分たちで安全性を保証することはできないという。
行政の言い分は、安全か安全でないかを判断するのは建築士。
でも建築士は境界ブロックについては建築基準では適合なので、そこは安全と判断できる。しかし、その上についている目隠しについては不明なので、自分では判断できない。そのため取り外してほしいと言っている。
個人的には非常にモヤモヤするのですが、ここで揉めても前に進まないので、クライアントにはもし行政から指摘されたら、目隠しを外して、検査終了後にもう一度取り付ける。その場合の費用はクライアント持ちになるということを話して、了承していただきました。
行政から指導が入るかどうか分からないため、これがこの状況での最善の方法だと判断したわけです。
万年塀の問題点と対処方法
さて、南側の境界ブロックについては一応、これで解決となりましたが、もう一つ東側に万年塀が残されています。
ここで万年掘りについて、おさらいしておきましょう。
<万年塀とは>
- 万年塀の正式名称は「鉄筋コンクリート組立塀」といい、鉄筋コンクリート製の支柱と、平板を挟んで造られた塀のことをいう。支柱の下部分には、固定するための基礎が地中に埋められている。
ところが実は、万年塀にいては建築基準法の決まりが特にありません。
なぜかというと万年塀は、「日本工業規格JIS A5409-1993鉄筋コンクリート組立塀構成材」とJISによって規定されている工業製品だから。建築基準法での細かい仕様は規定されていないのです。
そのため大きなヒビや傾きがなければ、通常そのままで新築物件を建てることが可能です。
ところが。
建築会社から万年塀については、新築時に建て直してほしいという要望が出されました。
その万年塀が危ないからというわけではなく、建築士が危ないとも大丈夫とも言えないからとのこと。
万年塀については建築基準法での規定がなく、建築指導でも明確な指導方法がないため、その安全性の判断は建築士に委ねられています。
しかし建築士としては、自分が安全と判断した万年塀に万一のことが起きた場合、自分が責任を負うことは避けたい。
そのため、念のために建て直してほしいというのです。
もちろん建て直したほうが安全ではあります。でもその場合、費用はもちろんクライアント持ち。せっかく境界ブロックは問題なかったのに、万年塀を建て直しとなったら意味がありません。万年塀は境界ブロックよりも費用がかさみますから、総予算に大きな影響が出てしまいます。
この点についても、杉並区の建築指導課に質問してみました。
回答としては、万年塀についても目隠しと同じく指導する決まりがないため、建築士が安全性に問題がないと言えば行政として指導することはないとのこと。
やはり、建築士が安全上問題ないと判断すれば、それで解決する話なわけです。
ところが、建築士は指導基準がないため、自分では判断ができないという。
私もすっかり頭にきてしまいました。
設計士は責任を取りたくないだけ。しかしプロとして、目視でも危険性の確認は十分できるのではないでしょうか。もちろん、建築に100%の安全はありえません。ブロックだけでなく建物そのものだって、地震があれば倒壊の可能性がないわけじゃない。だからこそ、現状の確認をプロの目で行うわけです。
それに万年塀にしてもお隣との境界線上に建っているわけですから、建て直しとなってもスムーズに話が進むとは限りません。
必要ないものに時間とコストをかけて建て直す必要は全くないわけです。
結局のところ、建築会社としてはどうしてもその万年塀のまま建築をするなら、売主である不動産業者の設計士から安全であるという書面を出してほしいと。
そのため、売主側の設計士が現状目視での安全性を確認した旨を重要事項説明書に記載するということで納得していただき、土地の契約へと進みました。
建築会社の設計士としては自分では安全性の保証は出せないが、売主が安全だと言っているならそれで問題ないという、これまたモヤモヤとした話で決着をつけることになったのです。
<万年塀のチェックポイント>
- 万年塀について、建築基準法での細かな規定はない。そのため既存の万年塀の安全性については、建築士がその判断を行う。
私としては納得し難い決着方法ではあったのですが、クライアントの利益追求が何より優先されます。建築士の言い分に矛盾があることを追求したい気持ちを抑えつつ、無事に契約が締結となりました。
まとめ
境界ブロックについては建築基準法においてしっかりとした規定があり、それに満たない既存境界ブロックがある場合、建築許可が下りない場合があります。
その場合は建て直しになるわけですが、境界ブロックはお隣さんとの共有所有物と「推定」されるため、勝手に壊したり建て直ししたりすることはできません。
そのため事前にしっかりと調査を行い、建て直しが必要かどうか、建て直しが必要な場合にはその費用負担や設置場所について、隣家の所有者も含めてしっかりと話し合うことが大切です。
一方で万年塀については、建築基準法での細かな規定がないため、建築士がその安全性を判断します。
しかし建築側の人たちはクライアントの総予算や立地よりも、建築のリクスヘッジのことがどうしても先にきてしまいます。
そのためたとえ予算が膨らむとしても、建て直しの方へ話を持っていくことも少なからずあるのです。
不動産エージェントとしてはクライアントの代理人として彼らの利益・願いの実現を第一に考えますから、むやみに建て直しを了承するのではなく、しっかりとしたプロの目で何が最善かを判断し、アドバイスできるようでなければなりません。
そのために、境界ブロックについてもこのようなチェックリストをもとに、安全性の確認ができるよう自分の目を育てていく必要があるでしょう。
(https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505000/d032305.html)
また建て直しが必要な危険なブロック塀の場合、道路に面しているものであれば自治体によっては補助金が出ることもあるので、利用できるものはしっかりと活用する。
不動産エージェントとしてクライアントのお役に立てるよう、境界ブロックについてもしっかりと勉強しておきたいですね。
この記事を書いた人
不動産エージェント 藤木 賀子

スタイルオブ東京(株)代表。
25歳で建築業界に入り、住宅・店舗・事務所・外構の営業・設計から施工まですべてを経験。
世界の建築に興味があり、アジア・北米を中心に建築を見て回り、いい家を追求すべく世界の家を研究。結果、いい家とは『お客様の価値観』にあることに気づき、自分が作るよりお客様の代理人としてお客様の想いを可視化・具現化・実現化することが出来る不動産プロデュースの道に。
これまでの経験とスキルを、不動産エージェントとして活躍したい人に向けて発信中。
≪不動産エージェントに興味があるかたはこちらからご相談ください≫